9月の敬老の日の由来や意味を保育園の子供が簡単に分かるようにまとめてみました。

![]()
はじめに
![]()
9月の第3月曜日が『敬老の日』で、この日から1週間が敬老週間です。
馴染み深い身近な高齢者さんを敬う敬老の日について『由来をまとめよう』という記事です。
敬老の日は主役の高齢者さんと共にお孫さんの活躍も同じくらい大切です。
敬老の日の由来と共に、保育園くらいのお孫さんを想定して伝承しやすい内容を伝える例文も添えました。
![]()
9月の敬老の日の由来や意味は?いきなりですが、大人向けの豆知識まとめ
![]()
敬老の日の由来は?
![]()
由来には、諸説があります。
社会福祉の祖と言われる聖徳太子が、四天王寺に四箇院を建てたのですが、そのうちの1つに悲田院がありました。
身寄りのないお年寄りを集めて養うという施設で、現在も形を変えて存続しています。
この建立した日が593年9月15日だったからという説です。
また717年9月15日に元正天皇が、
滝を訪れて養老の滝と命名して年号を養老として、
全国の高齢者に賜品を送ったのが由来とも言われます。
これらの由来を元にして、
1947年9月15日に兵庫県多可郡野間谷村、現在は多可町八千代区で村が
主催して「 敬老会 」を開催したのが敬老の日の始まりとも言われています。
もちろん農閑期であることや気候なども考慮した上で、命名したと言われています。
この小さな村の動きが、やがて県民運動につながり、
1951年に社会福祉協議会が「 年寄りの日 」としました。
戦後に誕生したこの日は、『 年寄りの日 』→『 老人の日 』→『 敬老の日 』と名前が変わっていきます。
敬老の日の意味
![]()
『 多年にわたり社会に貢献してきた老人を敬愛して、長寿を祝う日 』とされています。
多可郡の由来では、年寄りに感謝しつつ、年寄りの知恵を大切にして、
村を盛り上げようという村おこしの意味もあったと言われています。
敬老の日の当日の様子や贈り物は?
![]()
現在は各市町村主催で、敬老祝賀会が毎年、開催されています。
また老人会などを通じて、高齢者さんにお祝いの品を贈る地域もあります。
もちろん、お祝いの品やお祝い金に、これという決まりはありません。
敬老の日の主役である高齢者さんにふさわしい物を考えて贈り、
喜んでいただくことが趣旨になっています。
一般的には、食べ物では固いものや日持ちしないものを避けたり、
本人の好みから掛け離れるものを避けたりします。
服であったり、日常的に長く使えるようなものも、近年では喜ばれている様子です。
カードや便箋で日頃の思いを込めたメッセージを贈るなんてことも喜ばれています。
豆知識・諸外国の敬老の日は?
![]()
お隣の大韓民国の敬老の日は10月2日です。
…とどまらずに10月は月間を通じて敬老の月です。
中華人民共和国では五節句の1つである重陽の節句と合わせて旧暦の9月9日を高齢者の日と定めています。
昔のお祝いの文化は、中国を中心にアジア各国に伝播している傾向があります。
アメリカ合衆国では、9月第一月曜日の次の日曜日をNational Grandparents Day としています。
国連では10月1日を国際高齢者デーとして定めています。
他にも世界中で高齢者を敬う日があるのです。
![]()
敬老の日を保育園のお孫さんたちが分かるように説明するコツは?
![]()
どうです?
蘊蓄を並べてみると、なかなかに奥深いでしょう?
あれ?『 蘊蓄 』の中にお孫さんや子供の姿がない…。
じつは由来に、もう1つありまして…。
5月の節句に『 子どもの日 』があるのに、
お年寄りの日がないのはおかしいからという理由で出来たという説もあります。
年老いても、子どもに対抗する気概あふれる高齢者の町だったのでしょう…。
さて好奇心で溢れるお孫さんたち宛には、ここからです。
保育園では、いろんなことを覚えてきますが、敬老の日も当然、丁寧に教えてあげる必要があります。
これは保育園での学びの中核になる『 みんな仲良くしましょう 』『 人 ( 物 ) を大切にしましょう 』につながる部分です。
蘊蓄から、難しい言葉を除いて説明しても良いですし、アレンジも可能です。
保育園児に大切なことは、
『 おじいちゃん、おばあちゃん大好き 』 ( 愛情 )
『 いつまでも元気に過ごしてください 』 ( 長寿の願い )
と、保育園児はこの2つをメッセージに込められれば、100点満点だと言えますよね。
![]()
敬老の日の具体的な説明文
![]()
由来の例
![]()
働いて頑張った人が歳をとって、
働けなくなった人のために建物を建てたことが記念日になっている。 』 [ 養老の滝説 ] 『 むかし、お酒が流れる滝があって親孝行な息子が歳をとった親を連れて行って、
たくさんお酒を飲ませてあげた。
それを見た天皇陛下が養老の滝という名前を付けたのが敬老の日の始まりになっている。 』 [ 多可町説 ] 『 兵庫県の小さな村で、歳をとっても働きたくて仕方ない頑張り屋のお爺さんがいた。
力は出なくなったけど、若い人たちと力を合わせて頑張ることが出来たことが
敬老の日の始まりになっている 』
どうですか?
3つの説を並べてみると、高齢者を思い、助け、力を合わせるといった基本3拍子が揃っていませんか?
この話をした時に感じたことや気持ちを、
お孫様に自分の祖父母あてに
メッセージとして贈れるようにしてみるといかがでしょう?
もし遠方にお住まいであるとか、
ご事情がある場合は、孫の成長した写真にメッセージを添えて贈るだけでも、
立派な贈り物になるのではないでしょうか。
![]()
まとめ
![]()
『 敬老の日 』 には、市町村や自治会などで様々な催しも開催されています。
子供さんやお孫さんが、祖父母様と共に敬老会に参加してみても、1日を楽しく過ごせるでしょう。
また宴席を設けて、お食事会を開いてみても1日がお祝いとして和やかに進みます。
敬老の日に長幼の序を踏まえて、先人を拝してみるのは意義あることです。
先人である高齢者さんには、懐古して孫・ひ孫を眺めることで明日からの励みになります。
人生は将来を思い、過去を振り返り研鑽してこそ習熟していくものです。
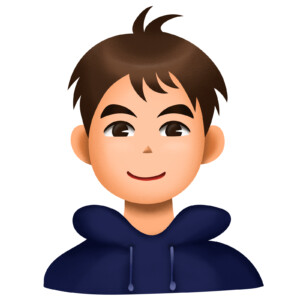
誠にありがとうございました。
お気づきのご感想を
是非、お寄せくださいましたら幸いです。
![]()
応援をよろしくお願いします]
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。